もうすぐ新年度が始まる3月中旬、手帳買い替えの時期になりますね。
3月中旬なので、店舗での現在の品揃えは、4月始まりの手帳がメイン。
ただ、3ヶ月前の1月始まりの手帳も割引販売されている、といったところです。
そうした中途半端なタイミングで、私は、1月始まりの手帳を、4月始まりの同一の手帳と比較して1500円安く購入しました。
しかし、その決断には少し悩みました。
その理由は、1月始まりの手帳は確かに安いけれど、既に1〜3月の3ヶ月分が経過しているから。
3ヶ月分が空白になるデメリットと、1500円の節約というメリットとどう比較して、どちらの手帳を購入すべきか。
さて、どちらが本当に価値がある支出だったのでしょうか?
価格の違う2つの手帳のコスパをどう比較するか
私が購入した手帳は、MARK’SというメーカーのB6サイズの手帳。


価格は、4月始まりのものは2670円である一方、1月始まりのものが1100円と、1月始まりの方が1,570円安い。
この1,570円という価格差が、3ヶ月分の空白を埋める価値があるのかどうか、直接は比較しにくい。
そこで、「使用できる月数」で購入価格を割って考えてみました。
すると、1月始まりのものがコストパフォーマンスが良いということに気づいたのです。
—
4月始まりの手帳は4月から12ヶ月分使える
→ 2670円÷12月 = 月額223円
一方、1月始まりの手帳は4月から9ヶ月分使える
→ 1,100円÷9月 = 月額122円
—
この計算では、1月始まりの手帳を1,100円で購入した方が、月当たりの手帳使用コストが約100円安くなることがわかります。
減価償却の視点を消費に応用する
これは、簿記などで使われる「減価償却」の考え方を適用したものです。
減価償却とは、要はモノの価値が時間とともに減少していく、ということを表した概念ですが、詳しくは下記のとおり。
—
(減価償却費とは?)
「減価償却費」とは、購入した資産(例えば、パソコンや車、建物など)の価値が時間とともに減少していく分を経費として計上するための仕組みです。
簡単に言うと、「物の価値が時間とともに減っていくことを計算して、その分を毎年の費用として分けていく」というものです。
例えば、ある会社が100万円のパソコンを購入したとしましょう。
このパソコンは、購入時の価値が高いですが、年々古くなり、性能も落ちていきます。
そこで、100万円を一度に経費にするのではなく、何年間かにわたって少しずつ経費として計上します。
この、少しずつ経費にする方法を「減価償却」と言います。
—
これを、日常の消費に応用してみると、たとえば「物をどれだけ長期間使用できるか」を視野に入れて、購入時の価格を元に実際のコストを割り出すことができます。
上記の手帳の場合、単に購入時の価格を比較するのではなく、その使用期間を踏まえた月当たりのコストで比較をすると、その差が1ヶ月あたり約100円、と評価されるということです。
手帳のように、使用期間が明確に決まっている日用品であれば、購入時に、この減価償却の考え方を適用できます。
すると、価格の比較ができ、より価値のある消費ができるようになる、ということです。
1月始まりの手帳の空白の3ヶ月をどう活用するか
さて、1月始まりの手帳を選んだことで、3ヶ月分が空白になってしまいました。
多くの人なら、この空白の期間を「もったいない」と感じるかもしれません。
でも、私は逆にこの期間を「振り返りのチャンス」として捉えました。
空白の3ヶ月を過ぎた日々の振り返りページとして利用し、過去にどんな出来事があったのか、を思い返すことで埋めることにしました。
購入した手帳の空白部分はただ無駄にするのではなく、自分で自由に使えることができる。
金額的な比較では得だとわかっても、無駄に3ヶ月空白が空くのは何だか気持ち悪い。
だったら、手帳を別の方法で使って埋めてしまえばいいだけのことだと思うのです。
使い方次第では、手帳そのものの価値が増すとも思います。
まとめ
「安いから」という理由だけで買い物をすると、すぐに後悔してしまうことがあります。
今回の手帳のように、価格と使用価値のバランスをしっかり見極めて選ぶことで、無駄な支出を減らし、より高い満足度を得ることができます。
何となく安いから、という理由だけで買い物をすると、必ずしも満足感は得られないかもしれない。
でも、その使用期間を考慮して、「減価償却」を日常の買い物に応用し、月額コストで考えることで、コストパフォーマンスを意識した賢い消費が可能になります。
また、単にコスパだけで買ったものが思ったように活用できない場合でも、工夫次第でその価値を最大化する方法を見つけることができます。
「この物を購入することで、長期的にどれだけの価値を得るか?」を意識することで、より賢い消費ができるようになるはずです。

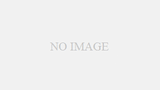
コメント