私は会社組織で働くことに馴染めないことに40代になってから気づき、FIREを目指している会社員です。
FIREするには、その定義通り、「FI(Financial Independence)」、つまり資産面での自立が必要で、日々、投資や節約による資産増加やキャッシュフロー改善に取り組んでいます。
ただ、日々お金のことを考え、行動していても、イマイチFIREが近づく感覚が持てないのです。
その原因は、いち会社員として毎月給料を受け取る生活を長年していた自分にこびりついている会社員マインドだと考えました。
これまでの会社員生活では、組織に守られながらも上司や部下など自分以外の他人のために自分の時間を使う、という働き方をしていました。
一方、FIREは他人の存在に左右されず自分の人生を生きることができる分、全ての責任を自分自身で負う生き方になるのだろう、という点が違う。
この会社員とFIRE民との間で必要となる価値観の違いを腹落ちさせないことには、いくら資産額を積み上げてもFIREできないのでは、と感じたのです。
そこで、そういう自分の価値観を変えたい。
価値観を変えるには、旅に出てみたことのない景色を見るとか、人と会うといった方法がありますが、大きな移動や支出を伴わずに価値観を揺さぶる方法として「読書」があります。
そういうわけで、今から5年以上前にベストセラーとなった、アドラー心理学を解説した『嫌われる勇気』を、改めて通読しました。
感想として、この本の核となる「課題の分離」「共同体感覚」「今ここを生きる」という考え方は、FIREを目指す上での心構えとも通じるものがあります。
以下に感想を記載します。
1. 課題の分離:他人の期待から自由になる
『嫌われる勇気』の核心の一つが「課題の分離」です。
自分の課題と他人の課題を切り離し、他人の人生に不要に介入せず、自分の課題だけに集中するという考え方です。
この考え方を理解する際に重要なのが、「その選択の結果を引き受けるのは誰か?」という視点です。
たとえば、親が子供に勉強を強制しても、勉強しなかった結果を引き受けるのは子供自身です。
したがって、親が子供の勉強をコントロールしようとするのは、他人の課題に首を突っ込む行為であるといえます。
FIREにおける「課題の分離」
この課題の分離は、FIREを目指す上でも非常に重要です。
私自身、会社員として働き続けることに違和感を覚えながらも、「上司の期待に応えなければ」「部下の不満に配慮しなければ」と、他人の課題に首を突っ込んでいました。
しかし、FIREという選択は「自分の人生を生きる」という覚悟です。
他人の期待に応え続ける会社員人生ではなく、自分の課題に集中して、自由な生き方に舵を切るためには、会社の課題や他人の評価から自分を切り離す必要があります。
2. 自己責任の重圧と向き合う覚悟
『嫌われる勇気』は、自分の課題に集中するということは「自己責任の世界に生きる覚悟」だと教えてくれます。
会社員という立場にいると、失敗しても「組織の責任」として逃げ道があります。
上司の判断ミスや組織の方針が原因なら、自分の意思決定の重さを背負わずに済むからです。
しかし、FIRE後の世界は違うのだろうと想像します。
経済的自由を手にしても、自分の人生の舵を握るのは自分自身。
そこで間違った選択をしても、言い訳はできません。
FIREは「自己責任の世界」
FIREを目指すということは、「完全な自己責任の人生を引き受ける覚悟」を持つことだと考えています。
会社という組織の枠組みを出て、投資の結果も、日々の選択も、すべて自分で引き受ける世界に足を踏み入れるということです。
会社員としての私は、他人の課題に首を突っ込んで苦しんでいるとも言えるし、その他人の課題に逃げ込んでいるとも言えます。
こうした価値観から脱却し、自分が、完全に自己責任の世界で生きることの重圧を受け止める必要があると痛感しました。
3. 本当の自由とは「坂道を押し上げる」こと
『嫌われる勇気』では、「本当の自由は坂道を転がり落ちることではなく、自らを押し上げていくことだ」と語られています。
欲望のままに流される生活は、一見自由に見えても、自分の人生の舵を手放している状態です。
逆に、自分の選択に責任を持ち、未来に向かって努力することが「自分の人生を生きる本当の自由」だというのです。
FIREにおける本当の自由
FIRE達成後に自分が何をしたいのか、今現在は明確には見えていません。
本当の自由とは、「自分で選んだ生き方に責任を持ち、自らを成長させていくこと」。
だとすれば、FIRE後に自由を謳歌するためには、経済的自由を得るだけでなく、「自分の時間をどう使い、どのように社会と関わっていくか」という問いに自分なりの答えを見つける必要があります。
4. 共同体感覚:自分の価値は「他者への貢献」によって見出す
『嫌われる勇気』の第四章で語られる「共同体感覚」は、FIRE後の生き方にも通じる概念です。
共同体感覚とは、自分を世界の中心に置くのではなく、他者の役に立ち、社会の一部として自分の存在価値を見出す感覚のことです。
人は、自分の価値を実感することで生きる勇気を持てるとされています。
FIRE後の「貢献感」の重要性
FIRE後の人生は、会社員としての役割を離れる分、「社会への貢献」という意味では空白が生まれるのではないかと想像します。
経済的自由を手に入れても、自分が誰にも必要とされていないと感じると、生きるモチベーションが薄れてしまうのかもしれません。
実際、FIREを達成した人も一定数は働きに戻る、といったニュースを見聞きします。
だからこそ、FIRE後は「自分にしかできない形で社会に貢献すること」を模索する必要があるのではないか。
何ら特別なスキルもない40代会社員である私がFIRE後にできることはあるのか、に対する答えを用意しておく必要があるように感じました。
5. 今ここを真剣に生きる:未来の不安を手放す
最後に、『嫌われる勇気』の第五章で語られる「今ここを真剣に生きる」という考え方です。
未来の不安に縛られるのではなく、過去の出来事にとらわれるのでもなく、「今の瞬間に集中して生きる」ことが大切だと説かれています。
FIREを目指す過程も「今ここ」を大切に
FIREは未来の自由のために行うものですが、未来ばかりに意識が行くと、今この瞬間を犠牲にしてしまいます。
私自身、資産運用や節約に気を取られて、日々の生活に潤いが失われている感覚を持つことがあります。
しかし、FIREを目指す過程において、「今を犠牲にしない」こととのバランスを保ちたいと感じました。
まとめ: 『嫌われる勇気』から得たFIREへのヒント
『嫌われる勇気』で説かれる「課題の分離」「自己責任の覚悟」「本当の自由」「共同体感覚」「今ここを生きる」といった概念は、FIREを目指す上でも有用な視点を与えてくれました。
FIREというとお金の問題に焦点が当てられることが多く、もちろんそれは重要ではあります。
ただ、お金に加え、自分のこれまでの生き方を振り返りつつ、FIRE後の人生でどのような価値観で生きていくか、考えるきっかけになりました。
『嫌われる勇気』は、FIREを目指す私にとって、「自由な人生を生きるための精神的な指南書」となりました。
これからも、この学びを胸に刻みながら、自分の道を進んでいきたいと思います。
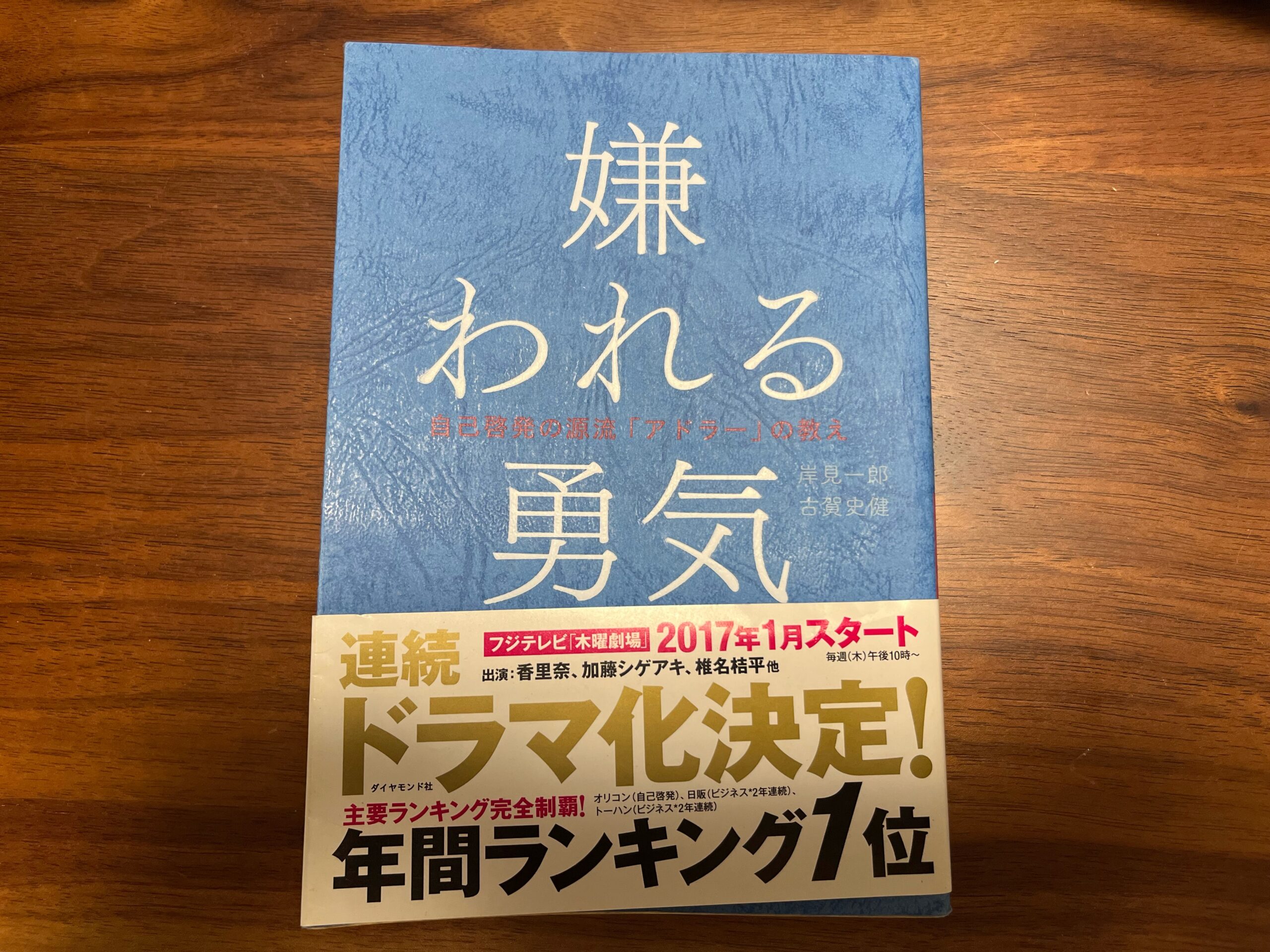
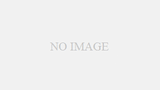
コメント