私は仕事に疲れてFIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指している会社員です。
なので会社で成果を出して出世したいという意欲はないものの、割り切って自由気ままに振る舞うほどの度胸もなく、ただ組織の中で日々消耗しています。
そんな私にとって、「どうやって会社との距離を保ちながら、自分の時間と心を守るか」 はとても大事なテーマです。
そんな中、佐久間宣行氏の著書『ずるい仕事術』を読んで、「FIREを志向しつつ組織に縛られている人」にも役立つエッセンスが多く詰まっていると感じました。
佐久間氏は元テレビ東京のプロデューサーであり、本著では、同氏がテレビ局での仕事の中で培ってきた「誰とも戦わずに抜きん出る62の方法」が綴られています。
この本には、会社と適度な距離を保ちつつ、自分の心を守りながら、FIRE達成まで持続的に働きたい私とっても学びがありました。
今回は、FIREを志向する会社員の立場から、この本を読んで感じたことを整理していきます。
(注)私は「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」のリスナーで、船長が大好きです。
【前提】自己啓発本は一般論ではなく自分にカスタマイズして読む
自己啓発本は、著者の成功体験やノウハウが詰まっていますが、そのまま自分に当てはめようとすると、理想と現実のギャップに苦しむことが多いものです。
私も「著者のようにできていない自分」に自己嫌悪してしまい、どうしてもプライベートの時間に自己啓発本を読むのが心理的に苦しく、本著も購入して2年以上、読まずに置いてしまっていました。
こうした自己嫌悪を乗り越えて自己啓発本を読む時には、著者の体験を一般論として読むのではなく、「記載内容を断片的に捉え、自分の状況に置き換えてカスタマイズする」視点が有効です。
『ずるい仕事術』も、組織の中で働くことを前提に書かれていますが、私の場合はFIREまでの“持久戦”を乗り切る戦略として応用するため、参考になる部分を抽出して読み取りました。
以下、その参考になった部分を紹介します。
会社との距離感を保つ3つの方法
本書で最も共感したのは、「会社との距離感を保つ方法」 についての記述です。
FIRE志向者にとって、会社はゴールではなく“通過点”です。
だからこそ、無理に全力を尽くすのではなく、ほどよい距離を保ちながら、メンタルを守ることが重要だと再認識しました。
① 悩みは因数分解して考える
組織の問題を、個人の努力でカバーするには限界がある。
でも、能力が足りないまま組織の悪口を言うばかりでは成長できない。
行く手を阻む壁は会社なのか自分なのか。
その見極めができてこそ、その努力が身を結ぶ。
出典:ずるい仕事術(佐久間宣行)
これは一般的にありがちな会社員の悩みにも通ずるもので、理不尽な上司の態度は変えられなくても、「その上司と関わる頻度を減らす」「期限を区切って様子を見る」といった自分でできる対処法に集中することで、冷静に状況を整理できます。
原因が自分にあるのか、組織(自分以外)にあるのかを見極め、自分でコントロールできることとできないことを切り分けて考えることで、すべきことが見えてくるし、メンタルコントロールがしやすくなるのだと思います。
② 自分の不得手を理由に断る
僕はゴールデンの番組をつくるのが苦手なんです。
全然、企画を思いつきません。
だからそれは得意な方にやっていただいて、僕は自分なりに精いっぱい、会社に貢献できる仕事をやらせてもらいたいです。
出典:ずるい仕事術(佐久間宣行)
これは佐久間氏が会社や上司の方針とぶつかりそうになった時に「自分を下げて断る」例として本著で紹介されている一文で、苦手な仕事を波風立てずに断る方法として、「自分の未熟さを理由にする」 というテクニックです。
私はそもそも相手方から頼まれた仕事を面と向かって断ることができなくて、無条件に受け入れて苦悶する、ということがよくあるのですが、それは体のいい断り方を知らないし、断って関係が悪くなるくらいなら引き受けてしまった方が楽、と考えてしまうこともあるためです。
ただ、そんな働き方は持続可能ではない。まして、目標がFIREであれば尚更。
自分の得手不得手を理解し、不得手である部分を伝える。それは、謙虚さを前面に出しつつ断るというテクニックになる。
これができれば、不要な負担を回避し自分の時間を確保することができます。
③ 期限を区切ることで無敵になる
仕事の先が見えない、つらい。
いまの会社にいつづけていいのかわからない。
サラリーマンならだれだって、一度はこんな悩みを持つだろう。
僕がおすすめしているのは、期限を決めてゴールを設定し、そこまでは全力で努力してみるということだ。
出典:ずるい仕事術(佐久間宣行)
「定年までこの仕事を続けなければならない」と思うと、息苦しくなります。
「3年までに目的の仕事ができなければ異動願いを出す」「あと1年仕事して面白くなかったら辞める」 といった期限を区切ることが本著では勧められています。
私自身、「あと〇年でFIREする」「あと〇回理不尽な目にあったら転職活動する」 と、数値で区切った期限を意識することで、組織の事情に振り回されがちな日々において心の安定剤としています。
会社との距離感を適切に保った後に、自分を出していく
以上①〜③では、「会社との適切な距離感の保ち方」について具体的な方法が紹介されていました。加えて本著では、与えられた仕事の中でも自分の感覚や面白さを見つけて活かす方法についても触れられています。
会社と適切な距離感を保つことで創出した心の余裕を土台として「自分が面白いと考えることを仕事に取り込む方法」 にシフトする。これは、FIREまでの通過点を会社に属しながらできるだけ快適にするためのカギになると感じました。
以下、本著で紹介されている「会社の中での自分の出し方」を紹介します。
④ つまらない仕事も工夫して面白さを見つける
だれでもできる「歯車」だと思っていた仕事が、ちょっとした工夫で「佐久間の仕事」に変わったのだ。
これが「仕事の楽しさ」を味わった、はじめての瞬間だったと思う。
不思議なことに、この日から現場が楽しくなった。
出典:ずるい仕事術(佐久間宣行)
これは、テレビドラマの撮影現場で、佐久間氏が「サッカー部の女子高生マネージャーが選手に渡す弁当を作る」という仕事の中に自分なりの工夫を凝らす中で面白さを見つけていくというエピソードに対する同氏の気づきを記した文章です。
私の場合、会社員でいたくないと感じる理由の一つが、意義を感じにくいルーティン業務に充てられている状態では、人生の時間をドブに捨てているような感覚になってしまう、というものです。
ただ、天地が転がってもつまらない仕事の目的を、その仕事自体に求めるのではなくて、「自分の工夫を持ち込む時間」と考えることで自分自身との勝負に持ち込むことができれば、面白みを発見できる余地が見出せるのでは、と思いました。
⑤ 自分の感覚を言語化して伝える
「だれかにおもしろい話」をしたいとき、そのネタはすでに自分の中にある。
でも、うまくそれを伝えられなければ、ただの「つまらない話」になってしまう。
その「おもしろさ」を「相手に伝わるかたち」でアウトプットする必要がある。
出典:ずるい仕事術(佐久間宣行)
自分のやりたいことや得意分野があっても、言葉にして伝えなければ組織では評価されません。ただ、目標がFIREである自分にとって、組織での評価はどうでもいいものではあります。
問題は、組織の評価を一切気にしない形だと、組織内での居心地が悪いことです(それを割り切れてしまえば無敵だけど、少なくとも自分にはそれができない)。できれば、組織に属している間の居心地も確保したいところ。
だから、せっかく④のとおりつまらない仕事を自分なりに創意工夫でおもしろいものにしようとしたのであれば、それを自分の中だけにとどめずに適切に言語化し、相手に伝えてみる。
結果としてそれが相手に受け入れられるかどうかは別として、組織内で自分なりの居心地のいいポジションは確保しやすくなるのではないでしょうか。
つまり、もしFIREを目指して組織には通過点として居るだけという認識であったとしても、「自分なりにおもしろさを見つけて相手に伝えようとする」という行為は、それだけ見ると手間には映るものの、結果としては組織の中で快適に過ごす手段となり、それはFIREまでの道のりを快適にする、ということにもつながるものと考えます。
まとめ:FIREまでの時間をどう立ち回るか
私の目標である「FIREまでの時間をどうやって自分のペースで乗り切るか」 という視点からこの「ずるい仕事術」を読んで改めて思ったのは、会社での立ち回り方一つで、FIREまでの道のりが楽になるか、消耗戦になるかが大きく変わる ということです。
さらに、本書には「キャリアの選択に一般論を持ち込むと、他人と同じ道しか歩めない」 という示唆もありました。FIREという、組織の中ではマイノリティに属するルートを「キャリアの一般論から外れた道」と捉えると、この示唆には非常に共感できます。
FIREは、まさに「自分だけの道を選ぶ生き方」です。『ずるい仕事術』は、組織における一般的なキャリアパスではないFIREを目指す人にとって、「会社と距離を保ちながら自分を守る技術」 を学ぶのにぴったりの一冊でした。会社に振り回されず、自分のペースでFIREに近づくために、「ずるく、賢く立ち回る方法」を意識したいものです。

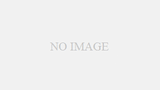

コメント