仕事のことが不安でメンタルが落ち込んでいるとき、「この不安な気持ちから抜け出せないのでは?」と思ってしまうことがあります。
私は過去に適応障害で休職した経験がある会社員で、仕事のストレスで不安を抱えることも多くあります。
特に不安な気持ちが強かった頃、不安から何とか抜け出したくて、あれこれ試してみました。
その取組の一つとして、自分の気分を30分ごとに「○(良い)、△(普通)、×(悪い)」で評価し、その時に取っていた行動と気分の変化との関係を記録していました。
その時の記録を見返すと、
・どんなに沈んでいる日でも、停滞した気分が変動する瞬間がある(×↔︎△↔︎⚪︎)
・気分が「△→⚪︎」「×→⚪︎」に上がる時の自分の行動にはいくつかのパターンがある
ことに気づきました。
今回は、この記録をもとに、「不安で停滞する心が上向いた6つの行動」を紹介します。
1. 散歩をする|物理的に体を動かす
心が沈んでいるときは、動くことすら億劫になります。
でも、とりあえず歩いていると、気持ちは少しずつ変わっていたようです。
仕事中、デスクから離れてとりあえず歩いてみる。
休日、近所の公園まで散歩する。
不安な気持ちを抱えつつも、できるだけ思考に意識を置かずに歩く。
体を動かしているうちに、思考が広がり不安に当たっていた焦点がブレていく感覚になります。
この時の経験を踏まえ、現在の私は、行き詰まったら「とにかく歩く」ことを意識していました。
2. 思考を書き殴る|不安を客観視する
不安で考え込んでいる時、頭の中でだけ考え続けると、思考がぐるぐる回って堂々巡りになります。
そういう時は、頭に浮かんだ思考や言葉をとにかく紙に書き出すと、心が落ち着く傾向にあったようです。
時に、書き出していく過程で、不安の原因になっていたことの解決に繋がるかもしれない「閃き」が降りてくることもありました。
そういう時は、まるで逆転満塁ホームランを打ったかのように、不安が興奮に変わりました。
自分の考えを書き出すことで不安の原因を客観視できるようになるとともに、言語化されることでその原因が突き止め解決の糸口が見つかりやすくなるのだろうと考えています。
この時の体験を踏まえ、現在の私は、自分の感情がいつでも書き出せるよう、常にペンとメモ帳を持ち歩くようにしています。
3. 目の前の作業に打ち込む|無心になる
「とりあえず手を動かす」ことも、心を動かす一つの方法です。
不安な気持ちの存在を受け入れつつ、それはそれとして今の自分にできることを見つけて、やる。
部屋が汚れているのであれば掃除をしたり、台所に置きっぱなしの食器を洗ったり。
仕事中、もしデータ入力など単純作業があれば、その作業に没頭する。
手元にある未処理のタスクをこなして少しでも進捗が出れば、停滞した気分が晴れる感覚があります。
あらかじめ、不安な時にこなすための単純作業リストを用意しておく仕組みにすれば、実践的です。
4. 感動するコンテンツに触れる|外部からの刺激で心を動かす
1〜3は全て自己完結する方法ですが、自分で動くことだけなく、外部からの刺激で不安が和らぐこともありました。
例えば、ライブや小説、漫画などのエンタメ・コンテンツに触れて感動した瞬間には、多くの場合に気分が「⚪︎」となっていました。
これを深掘りすると、コンテンツであれば何でもいいわけではないようです。
こうしたコンテンツを見ていると、その登場人物のセリフやシーンなどが、自分の置かれた状況とリンクしているように感じる時があります。
私の場合、自分の状況に置き換えた時に欲しかったセリフ等に出会うためにコンテンツに触れる、という感覚でエンタメを楽しんでいます。
5. 利害のない人に話を聞いてもらう|不安を吐き出す
不安な気持ちを誰かに聞いてもらった後は心が軽くなることが多かったようです。
当時通院していた心療内科の先生やカウンセラーに友人などに悩みを相談したことで、その原因は解決されていなくても心は晴れていました。
不安は、解決せずとも、「不安の気持ちを言語化できること自体」でも和らぐと実感しました。
この「言語化」は自分一人でも「2.思考を書き殴る」の方法により実践することができますが、言語化した話を人に聞いてもらうことも有効なのだろうと思います。
ただ、職場の上司や同僚、取引先など利害関係がある人にはなかなか自分の気持ちを打ち明けるのは難しいので、話す人を選ぶ必要はあると思います。
利害関係のない、相談できる人がいることは大切です。
6. 誰かに感謝される|「存在価値」を感じる
仕事上の利害関係者との関わりの中でも、「ありがとう」と言われた瞬間には気持ちが上向いていたようです。
基本的に仕事ではストレスを感じてばかりで目標もやりがいも感じることは少なかったですが、そうした中でも、上司や取引先から感謝の意味の言葉をもらえた時は、不安が影を潜めます。
しかも、感謝の言葉がもたらす不安の緩和は、その瞬間だけではなく、比較的長い時間持続します。
「ありがとう」と言われた後も暫く、その言葉を噛み締めることができたからです。
仕事で余裕が持てない時は特に、自分のことばかり考えてしまいますが、こうした時こそ利他精神が必要なのかもしれません。
それは、自分を犠牲にするということではなく、他人のために動いて、結果、感謝されることは、自分の気持ちを安定させることに繋がるから。
他人のため、というと大それたことのように聞こえますが、例えば、自分から誰かに「ありがとう」と伝えるだけでもいい。
その言葉は人の助けになるかもしれないし、結果的にそれは自分を助けることになる。
まとめ
以上、メンタルを病んでいた頃の自分の行動記録を振り返って、「不安な心を動かし上向かせる6つの方法」を紹介しました。
これらは、大きく分けると以下の2つに分類されます。
• 自分自身で動かす(散歩・書く・作業に打ち込む)
• 誰かの力を借りて動かす(コンテンツに感動する・話を聞いてもらう・感謝される)
自分自身がメンタルを病んでいた時の経験から考えると、不安に押しつぶされそうな時は、好きなコンテンツを見ることも、他人とコミュニケーションを取ることもしんどいものです。
だから、不安で心が停滞しているときは、まずは自分自身でできる「散歩・書く・作業に打ち込む」をしてみるといいのではないでしょうか。
加えて、困ったときは自分だけで何とかしようとせず、人やモノに頼ってもいいのだと認識しておくといい。
もし今、気分が沈んでいるなら、そんな自分にできそうなものを一つだけでも試してみるのがおすすめです。
心が動けば、次の一歩が見えてきます。

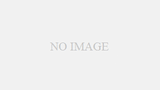
コメント